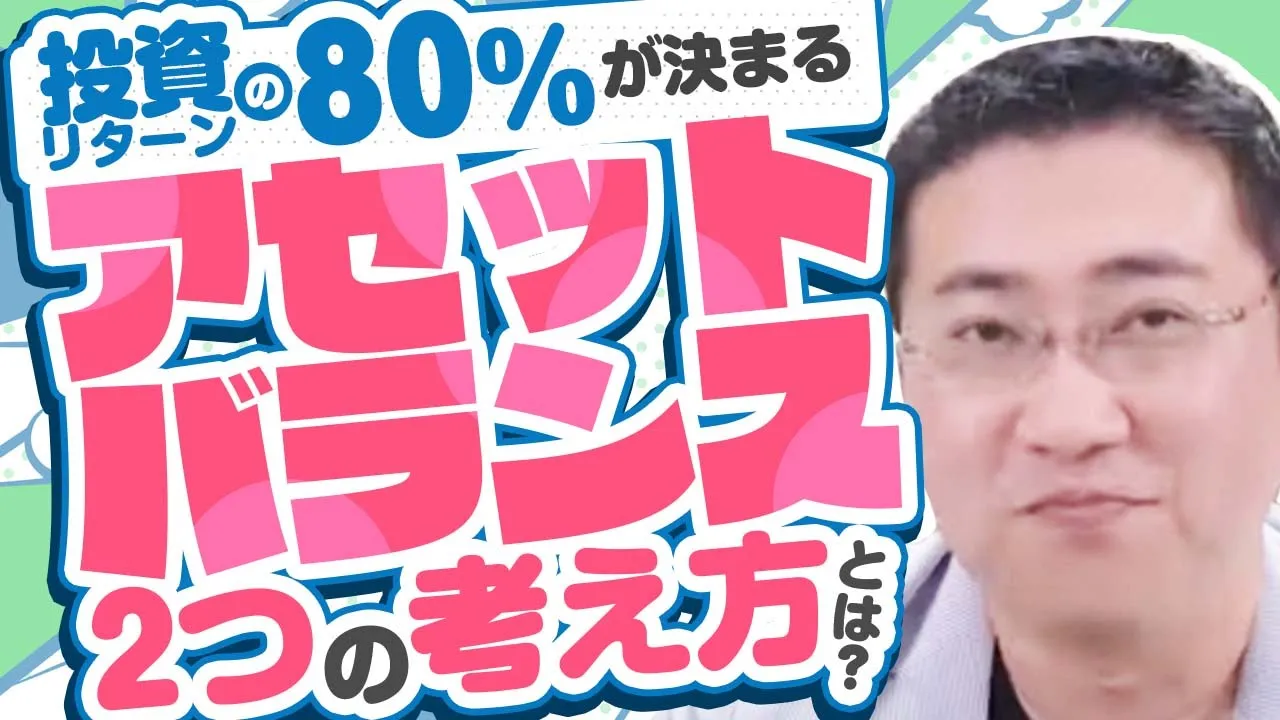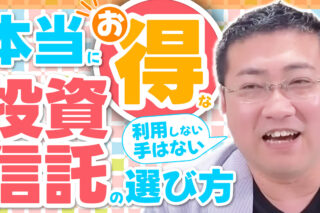今回はアセットアロケーションの根幹である「アロケーション(配分)」について解説します。
アセットアロケーションは、投資資金をさまざまなアセットに分配して、リスクを抑えた安全な運用を目指せる投資方法です。詳しい内容は「全世界投資の根幹アセットアロケーション」で解説しているので、まだご覧になられていない方はそちらを参照ください。
アセットアロケーション戦略において何よりも重要なのが、資産を振り分ける割合「アセットバランス」です。アセットバランスは、アセットアロケーション投資を成功させるための『カギ』となります。
ぜひ最後までご覧いただき、アセットアロケーションを実践できる段階まで知識をレベルアップしていきましょう。
アセットバランスとは資産配分の割合
アセットアロケーションを実施する際には、各アセットごとにあなたの資金を何%の割合で投資するか考える必要があります。
この、資産を振り分ける割合を「アセットバランス」と呼びます。

アセットアロケーション運用において、アセットバランスは投資結果の80%を決めます。
たとえば、マネーセンスカレッジは年利回り7%を目指しています。つまり、利回りのうち5.6%は投資資金をどのアセットにどれだけ配分するかのバランスで決まるのです。
投資結果の残り20%を決める要素は、金融商品や商品を購入したタイミングになります。アセットバランスさえしっかりと設定できればアセットアロケーション投資の恩恵を十分に受けられるということです。
アセットバランスの決め方は「購買力の維持・向上」がカギになる
まず、どのように割合を決めるのか、指針を考えていきましょう。
アセットバランスの指針となるものはさまざまあります。リスク許容度や利回りの目標など、人によって異なるでしょう。どの決め方も一長一短があり、決して間違っているわけではありません。
ただ、マネーセンスカレッジはアセットバランスを決める指針は「購買力の維持・向上」が大切だと考えています。
そもそも指針を考える際は、あなたが何のために投資をしているのかを思い出してください。
おそらく投資を始めたい方の多くは、お金を増やすことが目的ではないでしょうか。投資対象になる金融商品には値動きがあるため、価格が上がったり下がったりします。
私たちはお金を増やすことが目的なため、購入した商品の価格が上がるのを期待しますよね。価格が上がって儲けたお金で、何か商品やサービスと交換したいと考えているはずです。
この交換する力は「購買力」と呼びます。いわゆる、商品やサービスを買う力です。つまり、お金を増やす目的は「購買力を維持させ向上することが目的」とも言い換えられます。

アセットバランスの決め方はさまざまですが、投資の目的を前提に考えなければ本末転倒になる可能性があります。そのため、アセットバランスを決める際には購買力の維持・向上を重要視して考えましょう。
アセットバランス設定で大切な2つのアプローチ方法
アセットバランスを決める方針を「購買力の維持・向上」として、実際に割合を考えていきましょう。
アセットバランスの割合を考える際は、主に2つのアプローチ方法があります。
- 金融工学的アプローチ
- 社会学的アプローチ
それぞれのアプローチ方法で、考え方や算出されるアセットバランスが異なります。まずは違いを把握しましょう。
1.理論的に考える「金融工学的アプローチ」
金融工学的アプローチとは、さまざまな数値を用いて理論的にアセットバランスを導き出す考え方です。
そもそも、アセットアロケーション理論は金融工学から生まれています。
金融工学とは、予測が難しい金融商品の将来的なリスクについて、数学的な考え方で分析し論理化する学問です。
各アセットの過去データから得たリターンやリスクなどの数値を使って、あるアセットが将来どれぐらいの利益を得られるのか算出します。
その結果から、投資先の配分や注力すべきアセットなどを考えます。このような、複雑かつ緻密な計算を用いてアセットバランスを決める方法が金融工学的アプローチです。
2.世界情勢や生活環境などから求める「社会学的アプローチ」
2つめは、現実世界の経済状況や生活環境を踏まえてアセットバランスを考える「社会学的アプローチ」があります。
大切なのは、日本と先進国や新興国の経済規模の違いや各国の力関係などの部分です。
金融工学的アプローチと違い、社会学的アプローチでは理論的な計算ではなくGDP比率や時価総額などを参考にアセットバランスを導き出します。社会学的アプローチでは、年齢や投資可能な期間などの、運用を行う本人の状況も加味して考えます。
2つのアプローチ方法は掛け合わせるのが大切
2つのアプローチ方法がありますが、どちらでアセットバランスを求めるのが正解なのでしょうか。
結論から伝えると、2つのアプローチ方法を両方組み合わせて考えるとうまくいきます。
たとえば、金融工学的アプローチのみで考えてみましょう。
金融工学的アプローチは、過去のデータや未来を予測した数値などを使ってアセットバランスを考えます。
そのため、海外先進国の債券だけ割合が多くなったり、海外株式だけに資産が集中したりするなど、かたよった割合が導き出される可能性があります。
ひとつのアセットに集中したアセットバランスは、現実にそくしたものとはいえないですよね。
もし現実の経済状況と正反対の割合で構成されたアセットバランスに投資をした場合、運用はうまくいかないでしょう。
つまり、金融工学的な理論的数値だけでなく、社会学的な世界情勢や経済状況などの現実社会の部分も考えなければ、いびつなアセットバランスになるのです。

そのため、計算によって算出する金融工学的アプローチと全世界の構造や比率などを踏まえて考える社会学的アプローチは、2つを掛け合わせて考えましょう。
株式・債券・その他(不動産)のアセットバランス
2つのアプローチを両方使って、株式・債券・その他(不動産)のアセットバランスを考えていきます。
注意点として、実は金融工学的アプローチよりも社会学的アプローチを重要視しなければなりません。
アセットバランスを決める指針は、購買力の維持・向上。この目的を考えた場合、どちらかというと理論的な計算によって求められる金融工学的アプローチよりも、個人の経済状況や生活環境も含めて考える社会学的アプローチが大切になります。
株式・債券の比率は1:1が基本
株式と債券の比率は「1:1」がおすすめです。
なぜなら、株式や債券は景気が価格に大きく影響するためです。
株式は基本的に景気がいい時期に上昇します。この上がり方は、イメージしやすいのではないでしょうか。
一方、債券はどちらかというと景気が悪い時に上昇します。
つまり、一般的に株式と債券は反対に近い値動きをする関係性にあるのです。

株式や債券とは異なる値動きをするアセットが「その他(不動産)」です。
不動産は、基本的には景気がいい時期に価格が上昇します。
しかし、不動産市場の状況や金利の変動によっては、景気が悪い時期でも価格が上がることがあります。
つまり株式・債券・その他の値動きは、景気状況が大きく作用すると判断できますね。
ただ、今の景気がどれくらい良いのか、もしくは悪いのかの判断は投資初心者にとって難しいです。中級者・上級者であっても悩むことがあります。
先進国の少子高齢化の加速や世界の人口増加による水不足など、経済にとって不安定な要素はさまざまです。不安定な要素が多いにもかかわらず株式市場は好調になるケースもよくみられます。
このように景気の良し悪しを判断するのは難しいため、どちらに転んでも対応できるように株式と債券の割合は「1:1」で設定するのがおすすめです。
「その他」は資産全体の20%程度の割合
「その他(不動産)」の部分に関しては、投資資金全体の10%~20%程度の割合で考えましょう。
イメージとしては、あなたの家計に占める住居費の割合と同じです。
住居費は、家賃や住宅ローンの返済額です。おそらく多くの方は、家計に占める住居費の割合は20%〜30%ではないでしょうか。
マネーセンスカレッジでは「QGS」の考え方をもとに、家計の中で住居費が占める割合は手取り収入の22%に収めることを推奨しています。住居費(固定費)が25%を超える場合、家計が破綻する可能性があるためです。
アセットバランスにおいても「その他(不動産)」の割合は10%から20%がおすすめです。
住居費が手取り収入の22%を超えている方は、QGSのメソッドを学んで、家計を整えてから投資を始めましょう。
日本債券の割合は少なく設定する
株式と債券の割合は1:1ですが、その中でも「日本債券」の割合は低めの設定をおすすめします。
日本債券アセットの役割の一つには、アセットバランス全体のキャッシュポジション(投資しない現金)という役割があります。そのため、日本円建てでかつ安全資産である必要があります。
日本債券のアセットで運用されている金融商品は、一部会社が発行している社債もありますが、基本的に「日本国債」に投資しているという認識で問題ありません。
加えて「預貯金」があり、流動性や金利の違いは多少ありますが、両者はほとんど同じものです。日本円建てで安全資産であるという認識で問題ありません。
私たち日本人が日本円で投資を始める以前に、すでに日本債券(預貯金)を持っているケースがよくあります。
たとえば、急な支出にも対応できる一定数のお金(生活防衛資金)は預貯金で管理していますよね。退職金ももらえる金額が決まっているという意味で預貯金や日本債券とほぼ同じといえます。
誰もが、投資をするしないに関わらず、すでにほぼ同じものをそれなりにまとまった金額を持っているなら、日本債券アセットへの投資割合は少なくしておこうという考え方になります。
そのため、アセットバランスにおける日本債券アセットの割合は少し減らして考えましょう。
国や地域ごとのアセットバランスを考えよう
アセットの種類ごとの比率をイメージできたら、次は国や地域ごとで割合を考えます。国や地域ごとのバランスを求める方法は複数あるため、どのアプローチ方法を選ぶのかは人それぞれです。
そこでここでは、代表的な2つの決め方を紹介します。
1.全世界のGDP比率に合わせて決める方法
1つめの決め方は「全世界のGDP比率」に合わせてアセットバランスを考える方法です。
GDPとは、国の経済規模を図るための重要な指標。GDP比率に投資先の配分を合わせると、各国の経済状況に寄り添ったアセットバランスを決められます。
現時点のGDP比率で考えた場合、以下のような割合のアセットバランスになります。
- 日本:10%
- 海外先進国:60%
- 海外新興国:30%
ただし「先進国や新興国をどの国までにするのか?」という線引きや、今後の経済状況によってバランスが変わっていきます。
一概にこの数値が正しいとは言えないため、あくまでも目安として参考にしてください。
2.株式の時価総額に合わせて決める方法
2つめは「株式の時価総額比率」でアセットバランスを決める方法です。
株式の時価総額とは、上場している企業の株価に発行済株式数をかけた額です。簡単にいえば、時価総額が大きいほど企業価値が高いと判断できます。
株式の時価総額比率でアセットバランスを考えた場合、海外先進国に対する比率が大きくなります。
たとえば、日本で時価総額が大きい企業には、トヨタ自動車やソフトバンクグループがあります。
しかし、GoogleやAmazon、Microsoftのような海外の大企業は日本企業よりも高い時価総額です。
そのため、株式の時価総額比率で考えると海外先進国の割合が多い以下のようなアセットバランスになります。
- 日本:10%
- 海外先進国:80%
- 海外新興国:10%
時価総額は、時代によって占有率が変わります。バブル経済の時代は、世界と比べて日本企業の時価総額が非常に高い期間もありました。
現在は時価総額が高い企業の多くはアメリカ(先進国)に集中しています。2030年や2050年ごろには、アジア圏全体の時価総額だけで世界全体の40%以上を占めるともいわれています。
このように株式の時価総額は時代と共に変わっていくため、紹介したアセットバランスもあくまで参考程度に考えてください。
日本は海外に依存しているリスクを忘れてはいけない
ここまで、アセットの種類ごとの比率や国や地域ごとのアセットバランスを紹介しました。
ただ、ここで日本の「自給率」によるリスクを忘れてはいけません。
自給率とは、自国で消費する食糧やエネルギーなどを日本国内でどれくらい生産できるのか表すための数値です。
何度もいいますが、アセットバランス決定の方針は「購買力の維持・向上」です。
つまり、日本国内で何か物を買ったり、交換したりする「購買力」を大切にしている以上、アセットバランスと自給率は切ってもきれない関係なのです。
食料のほとんどは輸入に頼っている
知っている方も多いと思いますが、日本は食料自給率が非常に低く食べ物のほとんどを輸入に頼っています。
食料自給率とは、日本の食料供給に対して国内で生産している食料の割合を表す指標です。
食料自給率の数値は計算方法によって異なりますが、主に「カロリーベース」と「生産額ベース」の2つがあります。
カロリーベースは、1人あたりの消費カロリーに対して国内で生産されたカロリーがどれくらいあるのか示す指標。2018年のデータでは、カロリーベースの食料自給率は37%です。
一方、生産額ベースとは、国民に供給される食料全体の生産額に対してどれくらい国内で生産されたかを示す指標です。2018年のデータでは、生産額ベースの食料自給率は66%でした。
食料自給率の計算については、定義が曖昧な部分もあるので一概に正しいとはいえません。
ただ、カロリーベースと生産額ベースのどちらで考えても、日本は食料を海外に依存していることがわかります。
日本の資源自給率は10%以下
食料よりも海外に依存しているものが「資源」です。
私たちの生活に密接に関わっているものの中で「エネルギー」と「鉱物」の2つの資源は、ほぼ100%海外からの輸入に頼っています。
エネルギーとは、電気やガス、石油などです。日本のエネルギー自給率は、2018年のデータで「11.8%」と非常に低い数字になっています。
とくに、石油は日本でほとんど取れません。そのため、ガソリンや灯油などは海外の経済状況が影響しやすい部分です。
鉱物の代表例として、鉄や銅、鉛などに加えて、コバルトやニッケルといった「レアメタル」と呼ばれる鉱物があります。
普段の生活でも鉄や銅で作られた製品を使ったり、見かけたりする機会は非常に多いですよね。
ただ、そのほとんどは海外産です。
このように、私たちの生活は海外に依存しています。
つまり、私たちの資産の価値は海外の経済状況に大きく左右されるリスクがあるのです。
食料・エネルギー・鉱物に関しては、どれか1つが欠けると日常生活が破綻する可能性があります。それほど日本は海外に頼っているため、アセットバランスを決める際には「日本の自給率の低さ」を考えることは必然といえるでしょう。
日本に住む日本人ならではのドメスティックリスクにも注意する
アセットバランスを決める際は、海外への依存リスクに加えて、日本に住むことによる「ドメスティックリスク」も考えます。
たとえば、日本で飲食店やスーパーへ行った際に、接客やレジ打ちなどのサービスを提供してくれるのは誰でしょうか?おそらく、多くの場合は日本人ですよね。
また、国産牛や国産車など「国産の〇〇」に価値があると感じる方は多いのではないでしょうか。
このように、私たちの生活は国内でのみ提供され、国内でしか受けられないサービスに囲まれています。
そのサービスの対価として支払うのは普段から使っている「日本円」です。つまり、日本に住んでいる以上、日本円を使うリスクが発生しています。

日本は海外に大きく依存していますが、使用する通貨は日本円です。
国内の物価が上がったり、下がったりした場合は日本円自体の価値にも大きく影響します。
そのため海外への依存リスクだけでなく、日本に住んでいるリスクも考えてアセットバランスを考えることが大切です。
アセットバランスは人それぞれであり正解はない
さまざまな角度からアセットバランスの決め方をお伝えしてきました。
いろいろな考え方があり、どの決め方を採用したらいいのかわからないですよね。
結論として、アセットバランスには正解がありません。
アセットアロケーションの理論的には、過去の数字や未来予測の数字などを使ってアセットバランスを決めます。
ただ、安全で安定的な運用を目指すには、社会学的アプローチを重視したり、時価総額やGDP比率に加えて、日本の自給率、ドメスティックリスクも考慮しなければなりません。
GDP比率や時価総額だけでアセットバランスを決めるのは間違いではありませんが、これは全世界の人にとっての割合です。
日本に住み、日本円を使って生活する以上、日本人に合わせたバランスに調整する必要があります。
理論的には「日本債券」「日本株式」「その他(日本)」の3つが占める割合は、資産全体の10%程度です。
しかし、日本の自給率やドメスティックリスクを考えると15%から25%ほどの割合でも不思議ではありません。考え方によっては、もっと割合を増やしても間違いではないでしょう。

このようにアセットバランスには正解がないため、あなたの目的にあったバランスで投資を始めましょう。
自分なりのアセットバランスで投資を始めよう
適切なアセットバランスは人それぞれ違います。「これが正しい」といった割合はなく、あなたのライフスタイルや投資環境によって調整していくことが大切です。
まずは自分なりのアセットバランスを考えて、少ない金額から投資を始めてみてください。
自分に合うバランスを考えるのが難しいと感じる方には、万人受けするアセットバランスを会員制サイト「チーム7%」で紹介しています。アセットバランスについてさらに詳しく解説しているコンテンツも豊富に用意しているので、まずは万人に向いている割合で投資をして、そこから自分に合わせたバランスに調整してみてはいかがでしょうか。興味がある方はぜひ入会を検討してくださいね。
累計20,000人以上が受講!チーム7%プレ講座を無料公開中
マネーセンスカレッジでは投資をしたいけど何から始めたらいいかわからない方のために会員制チーム7%を運営しています。
「チーム7%は本当に自分にできるのかな?」というような疑問はないでしょうか。せっかく入会するのにミスマッチは避けたいですよね。私たちも同じ気持ちです。
この講座では「マネーセンスカレッジの投資方法の秘密」や「なぜ誰でも簡単に7%運用ができるのか」などの疑問にお答えしています。あなたが今抱えている投資やお金、チーム7%に関する不安を解決してください。
こちらの無料プレ講座は月額1,815円(税込)で提供しているチーム7%の凝縮版です。20年間で累計20,000人以上が視聴しており、資産運用を始められています。
内容をくわしく知りたい方は以下のフォームからご視聴ください。