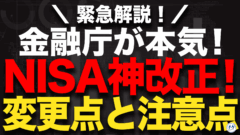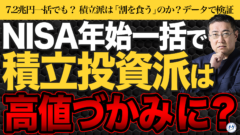【金融所得課税】NISAは本当に守られるのか?政府の「投資増税案」を解説!
最近、日本経済新聞で政府が金融所得に社会保険料を課す検討に入ったというニュースが話題になっています。この内容について、多くの投資家が不安を感じているのではないでしょうか。
確定申告をしている人としていない人で社会保険料の負担が異なる現状を受け、政府は金融所得の把握を進めて適切な負担を求める制度設計を進めようとしています。しかし、この提案には多くの問題点が指摘されており、投資家目線で見ると非常に懸念すべき内容となっています。
キーポイント
金融所得が医療や介護保険料に反映される? (00:01:23)
今回の検討内容は、確定申告をしている人としていない人で社会保険料の負担が異なる点を解消することが目的です。特に国民健康保険料の話であり、サラリーマンの被用者保険は検討対象に含まれていません。
国民健康保険料に加入している事業者や高齢者が主な対象となります。現在、NISA口座での取引は確定申告に含まれませんが、特定口座の源泉徴収なしや、源泉徴収ありでも損益通算のために確定申告をしている人は対象となる可能性があります。
日本経済新聞の試算によると、株式所得が50万円ある人の場合、国民健康保険料が年間5万円上昇するとされています。さらに介護保険料も上がり、窓口負担も1割から2割に増加する可能性があります。
発端は「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)の注釈」 (00:04:29)
この議論の発端は、6月に発表された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」にあります。その中で、「医療介護保険における負担への金融所得の反映に向けて、税における金融所得にかかる法定調書の現状も踏まえつつ、マイナンバーの情報連携等の課題、負担の公平、関係者の事務負担に配慮しながら具体的な制度設計を進める」と記載されています。
これは、確定申告をしていない人でも金融所得を把握して適切な負担を求めるという内容です。税務署は把握しているが、市町村や保険者が把握しづらい状態を解消することが狙いとなっています。
厚生労働省は被用者保険(サラリーマン)への適用は困難と判断しており、まずは国民健康保険から先行して始めるという方針のようです。
社会保険料等に金融所得の正しい反映はできるのか (00:09:14)
この提案には根本的な問題があります。不公平感があるなら、確定申告をしても社会保険料に含めなければ良いだけの話です。そうすれば全員が同じ条件になり、不公平感は解消されます。
より効果的な解決策として、1億円の壁を解消する税制改革が考えられます。高額所得者、特に金融所得の高額所得者に対して税率を引き上げ、その税収を社会保障費に充てるという方法です。フランスなどでは類似の仕組みが既に導入されています。
現在の提案は技術的に非常に困難で、実現可能性に乏しいものです。金融機関や市町村に大きな事務負担をかけ、かつ被用者保険には適用できないという欠陥があります。
背景には、高齢者の平均的な金融純資産(金融資産から金融負債を引いた額)が1,600万円あるのに対し、現役世代は住宅ローンなどでマイナスになっているという格差があります。この格差を是正する必要性は理解できますが、手法が問題です。
まとめ
今回の政府提案は、問題意識自体は理解できるものの、手法として非常に問題があります。実現困難な制度設計を進めるよりも、金融所得税率の引き上げや、NISAの非課税枠を活用した公平な税制改革を進める方が現実的で効果的です。
NISAの1,800万円の非課税枠を活用すれば、若い世代も長期投資の恩恵を受けられ、それを超える部分について適正な課税を行うことで格差是正が可能です。今後の政策動向に注目しつつ、投資家として適切な情報収集と判断を行うことが重要です。
この提案が実現される可能性は低いものの、政治的な議論の動向を注視し、投資戦略に影響を与える可能性も考慮しておく必要があります。
またこちらの動画「【石破おまえもか!?】国が金融所得課税を引き上げたい本当の理由【きになるマネーセンス769】」では、金融所得課税の仕組みや、国がこの制度をどう変えようとしているのかについて詳しく解説していますのでぜひご覧ください。