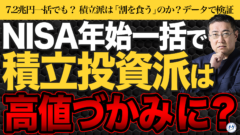収益性か安全性か?40代の資産戦略
40代を迎えると教育資金や老後の備えといったお金の悩みが現実味を帯びてきます。貯蓄すべきか投資すべきか迷いが尽きない中で最適な資産運用を見極めるには何が必要でしょうか。
本記事では資産運用の考え方から貯蓄と投資のバランスの取り方、教育資金と老後資金の両立法までを丁寧に解説します。これからの資産形成に悩む方の指針となる内容です。
キーポイント
日本人の資産運用意識に変化:収益性志向の高まりとその背景(00:01:09)
近年、日本人の金融商品に対する意識に大きな変化が見られます。従来は「元本保証」や「安全性」を重視する傾向が強かったものの2021年以降、特に「収益性」を重視する層が急増しています。
背景にはいくつかの要因があります。まず挙げられるのはコロナ禍による経済不安とそれに続く世界的なインフレの進行です。日本国内においても物価上昇が続き従来の貯蓄中心の資産形成では実質的な資産価値を維持できないという危機感が広がっています。これにより多くの人々が将来的な資産防衛の手段としてより高い収益を見込める投資商品に目を向け始めたのです。
一方で安全性や流動性を重視するという声も依然として一定数存在しています。特に元本割れのリスクを避けたいという意識から投資には踏み切れないという人々も多く、調査によれば「リスクのある商品を保有しようとは全く思わない」と答えた層も半数近くにのぼります。
このような二極化の背景には労働による収入の維持を選ぶ人々の存在もあります。日本でも名目賃金の伸びは緩やかながらも続いており「働き続けることでインフレを乗り越える」と考える層も一定数存在します。彼らにとって投資は不確実性の高い選択肢であり、代わりに「労働=安定した収入」を維持することを好む傾向があります。
資産運用は「期間」で決まる:貯蓄と投資の使い分け方(00:08:27)
収益性を求める人が多くなったとはいえ自身の資産を100%収益性の高いものにするというのは現実的ではありません。かといって100%貯蓄とするのは非効率的です。
考えるべきはなにより自身のファイナンシャルプランです。いつまでにいくら必要なのかをはっきりさせることでどれくらい収益性の高いものに回すべきかが見えてきます。そのどうやってお金を用意するか方法を考えるのが資産運用です。
資産運用を成功させるために最も重要な要素のひとつが「期間」です。使う予定のあるお金についてはその使用までの期間が短ければ短いほど投資よりも貯蓄を優先すべきです。
なぜなら投資は短期間で利益が保証されるものではなくむしろ短期的な価格変動に大きく影響を受けるリスクが高いからです。
長期投資では最低でも10年以上の運用期間が望ましいです。これは市場の変動を長期間で平準化することで安定したリターンを得られる可能性が高まるためです。さらに言えば使う直前に相場が下落してしまうとそれまでの努力が水の泡になる可能性があるため資産を使うまでにはもう少し余裕が欲しいところです。
リスクを回避するためには少なくとも3年、できれば5年のバッファを用意しておくべきでしょう。
つまり投資できる期間は「使うまでの年数」ではなく「使う3年前までの年数」と考えるべきです。10年先に使う資金なら投資に回せる期間は実質7年。この前倒しの考え方が投資の本質です。
このように投資とは「お金を前倒しで用意する行為」と言えます。将来に必要な資金をいまから少しずつ準備し複利の力を活用して育てていく。そのためには投資に適した資金とそうでない資金をしっかり区別し戦略的に使い分けることが大切です。
教育資金と老後資金の準備:タイミングと優先順位の見極め(00:11:41)
40代にとって特に悩ましいのが子どもの教育資金と自分自身の老後資金の両立です。この2つはほぼ同時期に大きな金額が必要となるため、計画性のない資金準備では対応が難しくなります。特に40代になってから子どもが中高生に差し掛かると大学入学までの期間が短くすでに投資に回す時間的余裕は少なくなっています。
大学入学まであと6年しかないという段階では長期投資による収益を得るには期間が足りません。そうなると選択肢は貯蓄一択となり、リスクの少ない手法で計画的に積み立てていく必要があります。逆に子どもが生まれたばかりなら18年という長い準備期間があるため積極的に投資を活用することで資金形成の効率を高めることができます。
一方で老後資金はどうでしょうか。40代の時点であれば60歳あるいは65歳、さらには70歳以降の引退を視野に入れることで15〜30年の運用期間を確保できます。この長さがあるからこそ老後資金には長期投資が有効なのです。
教育資金と老後資金はしばしばトレードオフの関係にあります。とりわけ30代後半〜40代で子どもを持った場合、教育資金の支出と老後資金の準備時期が重なってしまうためどちらか一方に偏った準備では不安が残ります。
こうした課題を乗り越えるためには工夫も必要です。たとえば子どもの大学資金を一部奨学金でまかない浮いた資金を投資に回すという戦略もあります。親が最終的に学費を肩代わりする形にすることで運用期間を延ばしつつ収益性を確保することが可能になります。もちろん奨学金の活用には家庭内での話し合いやお子さん自身の金銭感覚の教育も必要になります。
こうしたバランス感覚は資産運用において非常に重要です。すべてを投資に頼ることもすべてを貯蓄でまかなうことも現実的ではありません。時期や目的、家族構成によって優先順位を明確にしその上で柔軟に戦略を立てることが求められます。
夫婦で考えるこれからのお金:運用リテラシーの重要性(00:17:25)
資産運用は個人の問題であると同時に家庭全体の課題でもあります。特に夫婦で家計を共にしている場合、どちらか一方だけが運用に詳しくもう一方が無関心という状態ではいざという時に問題が起こる可能性があります。
理想的なのは夫婦が共にライフプランを共有しお互いに資産運用の考え方を理解している状態です。投資方法や資金の使い道を毎年見直す機会を設け、将来の生活設計に対する共通認識を持つことが必要です。たとえば1年に1回、年末などに夫婦で家計を振り返り、収支のバランスや資産状況を確認するだけでも家計運営の精度は大きく高まります。
また家族内で資産管理の担当者を固定してしまうと知識の差が広がりリスクが集中してしまう可能性があります。将来的にどちらかが判断不能な状況に陥った場合に備え普段から話し合いを通じて理解と信頼を深めておくことが大切です。
資産運用には継続的なメンテナンスが不可欠です。決して「ほったらかし」でうまくいくものではなく将来の変化に柔軟に対応するための調整が必要です。インフレや市場の変動、生活環境の変化など想定外のことが起きるのが人生です。だからこそ毎年資産状況をチェックし必要であれば投資額や貯蓄額を調整することが重要です。
このように資産運用において最も大切なのは「計画性」と「対話」です。家庭内で資産運用についてしっかり話し合える関係を築くことが将来にわたる安心の鍵となるのです。
まとめ
資産運用は単なる「お金の増やし方」ではありません。自分自身や家族の将来のためにいつ、いくら必要になるかを見極めその準備を確実に進めていくための戦略です。特に40代は教育資金と老後資金という大きな支出を控えた時期であり資産運用の重要性が一層増してきます。
貯蓄と投資は対立するものではなく目的と期間に応じて使い分けるべきものです。短期間で使う資金には貯蓄を、長期間に渡って備える資金には投資を。そうしたバランス感覚を持つことが豊かな人生を支える柱となります。
収益性だけを追い求めるのではなく安全性や生活の安定も意識しながら自分に合った運用スタイルを見つけてください。その中で貯蓄と投資をバランスよく取り入れた賢い選択がこれからの人生をより豊かにする鍵となるのです。
またこちらの動画「《学費で貯金がなくなる前に!》教育資金と老後資金を同時に用意する方法」では本記事でも紹介した教育資金と老後資金をどちらも用意する方法をさらに詳しく解説していますのでぜひご覧ください。