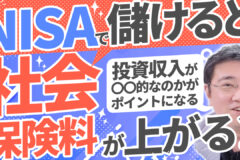S&P500暴落!気絶投資の限界とは
本記事では「トランプショック」による市場の急落を背景に「気絶投資」では乗り越えられない暴落相場への対応法をわかりやすく解説します。
S&P500やオルカンといった代表的な指数の下落状況、過去の暴落との比較、そしてこれからの資産運用に必要な考え方まで網羅的に紹介。投資初心者から中級者まで長期的な資産形成を目指すすべての方に役立つ内容です。
キーポイント
トランプショックと株価暴落の現状(00:00:00)
2025年春、アメリカ大統領トランプ氏の「関税強化発言」に端を発したいわゆる“トランプショック”が世界の株式市場を混乱させています。S&P500は円換算で年初来約19%、オルカンも約15%を超える下落を記録しました。さらに為替もドル円ベースで約9%円高が進行しており為替変動と株価下落のダブルパンチを受けている状況です。
こうした状況の中「気絶投資」つまり何も見ずに市場から距離を置く手法が一部では推奨されています。しかし情報が洪水のように押し寄せる現代において完全に目を閉じていられる投資家は稀です。新しいニュースが流れるたびに不安を掻き立てられ落ち着かないという声が多く上がっています。
気絶投資が一定の効果を持つのは長期投資の基本方針が揺らいでいない場合に限られます。しかし今回のように政策転換や政治リスクがダイレクトに市場へ影響を与える場合、無視し続けることは果たして正しいのでしょうか?
現時点での株式市場と為替相場の動向を解説しつつ「気絶投資」が有効となる条件とその限界についてしっかり理解しておくことの重要性を掘り下げます。
S&P500の現状把握(00:01:14)
4月11日時点の指数をみるとS&P500がドル建てで約8.8%と大きな下落を見せています。これらの数字には円高も加味されており米国中心に投資していた人にとっては非常に厳しい状況と言えるでしょう。
また為替の動きも注目すべき点です。ドル円は年初来で約9%下落しておりこれは「円キャリートレード」の巻き戻しが背景にあると考えられます。円キャリートレードとは低金利の円を借りて高金利通貨や資産に投資する手法ですが市場のリスクオフムードによってこの流れが逆転し円が買い戻される傾向が強まっているのです。
こうした急激な為替変動と相場下落のダブルインパクトは特に海外資産に集中投資していた投資家にとって大きな打撃です。為替と株価の両方にリスクがあることを改めて再認識する必要があります。
気絶投資の限界と正しい対処法(00:06:30)
投資において最も避けたいのは「無自覚な無関心」です。気絶投資とは自分の投資方針がブレていないことを確認した上で、市場を無視するという一つの手法ではあります。しかし情報を遮断してしまうことで戦略の見直しや軌道修正のタイミングを逃す危険性もあるのです。
今回のトランプショックのように予想外の政治的リスクが市場を動かす場面ではその影響が自分の投資戦略にとって「想定内」なのか「想定外」なのかをしっかり判断する必要があります。例えばS&P500を主軸にしている投資家であれば「アメリカの成長力は長期的に見れば揺るがない」と確信しているかが問われます。
投資戦略の根幹が崩れていないかどうかを確認し問題がなければ淡々と続けることも正解です。一方で今回の下落が想定外だったり自分自身のリスク許容度を超えていた場合は戦略の見直しが必要です。
こうした“見直しのタイミング”を逃さないためにも暴落時こそ冷静に市場を直視し自己チェックを怠らないことが求められます。
過去の暴落と比較して見える教訓(00:13:21)
投資の世界では過去のデータから多くを学ぶことができます。リーマンショック時には先進国株式が約58%下落し元に戻すには138%のリターンが必要でした。これに要した時間はおよそ6年。さらに日本リートはそれを上回る下落率と回復期間が求められました。
このように大きな下落はその分だけ回復に膨大な時間がかかるため「大きく負けない投資戦略」が重要になります。特に長期投資家にとっては一度の大暴落がその後の資産形成に与える影響は計り知れません。
このことからも「一つの資産に集中しない」「時間分散を取り入れる」といったリスク管理がいかに重要であるかが分かります。つまりリーマンショックのような危機が起こったとしても、自分の資産が長期的に回復できるよう適切に設計されていることが求められるのです。
長期投資で見落とされがちな「時間のスパン」という視点(16:50)
投資で避けて通れないのが「価格変動」つまり値動きの振れ幅です。そしてその値動きがどう見えるかは「期間(スパン)」によってまったく異なってきます。この視点を理解しておくことが冷静な資産運用の第一歩です。
過去のリーマンショックでは1年半で約60%の下落がありました。単純に18ヶ月で割れば毎月3.3%の下落と考えがちですが実際にはその期間中に急激な下げが連続する“乱高下”があったのです。つまり実際の体感は「穏やかな下落」ではなく「精神的に打撃を受けるような急落の連続」だったということです。
このことからもわかるように長期のスパンで「投資戦略を維持できるかどうか」は短期的な変動への“精神的耐性”とも密接に関係しています。ではこのような局面においてどのような姿勢が投資家に求められるのでしょうか。
それは「叩き起こされるたびに不安になる」のではなく「自分の投資戦略が今でも通用するのか?」を自問自答し確認するという姿勢です。具体的には「投資方針は崩れていないか?」「想定していたリスク範囲内か?」という2つの観点が重要です。
もし今回の出来事に対して「怖い」と感じたのならばそれは現在採用している投資戦略が自分の精神やリスク許容度に合っていない可能性があるということです。これは「間違っている」のではなく「見直すタイミングが来た」というシグナルかもしれません。
今回のトランプショックのような下落局面では「短期の乱高下に動揺せず、戦略の根本を見直す機会」と捉えることが非常に重要です。そしてその戦略が自分に合っているかどうかを再確認することで次なる暴落にも備えることができるのです。これはまさに投資家としての成長の瞬間でもあります。
まとめ
トランプショックのような突発的な市場変動は長期投資家にとって避けられない試練です。こうした時期にこそ自分の投資戦略が本当に機能しているか見直す絶好のタイミングでもあります。気絶投資に頼るだけでなく冷静な現状把握と自らの判断軸を持つことで長期的な資産形成への道を着実に歩んでいけるでしょう。
今後も不確実性が増す中で「リスクを抑えつつリターンを得る」投資スタイルとして全世界投資やアセットアロケーションの重要性が一層高まることは間違いありません。自分に合った戦略を見つけ長期的視点で腰を据えた資産形成に取り組んでいきましょう。
またこちらの動画「【裏の狙い】トランプ関税ゼロの唯一の国とその真相。世界と日本への影響は?」ではトランプ関税の真の狙いについて解説していますのでぜひ参考にしてみてください。