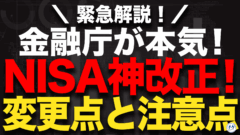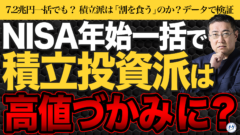iDeCoの受け取り方法を徹底解説!一括vs年金、どちらが賢い選択?
りそなグループがiDeCoの受け取り手数料を無料化するというニュースが話題になっています。このニュースを機に、iDeCoの賢い受け取り方について詳しく解説します。
iDeCoの受け取り時には毎回440円程度の手数料がかかっており、これが年金受け取りを選択する際の大きな障壁となっています。今回のりそなグループの取り組みは、この問題を解決する画期的な動きと言えるでしょう。
りそなグループのニュースリリース(1:26)
2025年7月1日、りそなグループがiDeCoの給付金受け取り手数料無料化を発表しました。これは国内初の取り組みで、2025年7月1日以降の受け取り分から手数料が0円になります。
この発表により、手数料合戦に新たな1ページが刻まれることとなりました。現在のところ、他の金融機関からの追従発表はまだ出ていない状況です。
iDeCoでかかる手数料(1:55)
企業型確定拠出年金の場合は企業が手数料を負担してくれますが、iDeCoは自分で支払わなければなりません。iDeCoにかかる手数料を整理してみましょう。
加入時には初回のみ2,829円の手数料が必要です。運用時には国民年金基金連合会に月額105円、事務委託先金融機関に月額66円を支払います。また運営管理手数料として0円から数百円が設定されていますが、多くの金融機関では0円となっています。そして給付時には1回あたり440円の手数料がかかります。
この給付手数料440円が、特に年金受け取りを選択する際の大きな負担となっているのです。
給付手数料440円が足かせになっている理由(2:56)
現在、iDeCoの受け取り方法として約9割の人が一括受け取りを選択しています。残りの1割が年金受け取り(併用を含む)を選択していますが、この偏りには給付手数料が大きく影響しています。
一括受け取りの場合は手数料が440円の1回限りで済みますが、年金受け取りでは受け取り回数分の手数料が発生します。年6回受け取りの場合は年間2,640円、20年間継続すると合計52,800円の手数料負担となります。
20年間で5万円を超える手数料は決して無視できない金額です。この手数料負担を嫌って、本来は年金受け取りが適している人でも一括受け取りを選択するケースが多いと考えられます。
年金受け取りは退職所得控除が満額使える場合や、退職金がない場合に税制上有利になることが多いのですが、手数料の存在がこの選択を阻んでいるのが現状です。
手数料無料でどれだけお得?(4:42)
確かに440円の手数料は固定値であり、20年間で52,800円という金額は大きいものの、これだけで受け取り方法を決めるべきではありません。重要なのは、総合的な資産運用戦略を考えることです。
iDeCoの受け取り方法には3つの選択肢があります。一時金として一括受け取りする方法、年金として分割受け取りする方法、そして一部を一時金で受け取り残りを年金として受け取る併用という方法です。
多くの人が一時金を選ぶ理由は税負担を軽減したいからですが、まとまった資金を一度に受け取った後の運用も考慮する必要があります。
iDeCoは運用時非課税という大きなメリットがあります。一括で受け取った資金をその後特定口座で運用すると、運用益に対して20%の課税が発生します。一方、iDeCo内で年金受け取り崩しながら運用を継続すれば、引き続き非課税での運用が可能です。
また、NISAの非課税投資枠には年間360万円という上限があるため、まとまった資金を一度に非課税で運用することは困難です。この点からも、年金受け取りによる長期運用継続にはメリットがあります。
理想的な老後資産設計を考える際のモデルケースとして、年金の繰り下げ受給を前提とした戦略が有効です。60歳でリタイアする場合、夫婦2人の平均的な生活費は月27万円程度となります。5年間で約1,500万円、10年間では約3,000万円が必要な計算です。
3,000万円の老後資産があれば、10年間年金受給を繰り下げることが可能です。この間はiDeCoや他の運用資産を取り崩しながら生活し、70歳から年金受給を開始する戦略が考えられます。
このような資産設計を行う場合、iDeCoを年金受け取りしながら運用を継続することで、リスクを国に転嫁しつつ自分の運用資産を効率的に活用できます。
現在一括受け取りが多い背景には、iDeCo加入者の多くが数百万円程度の受け取り額にとどまっていることがあります。しかし、今後は状況が大きく変わると予想されます。2020年頃からiDeCoが本格的に普及し、拠出限度額も月68,000円へと引き上げられました。20~30年の長期積立により1,000万円台の受け取り額が現実的になってきています。
このような背景から、将来的には年金受け取りを選択する人の割合が増加すると考えられます。特に40代以降の現役世代は、従来の退職金・企業年金制度とは異なる老後資産設計が必要になるでしょう。
試算してみた(13:50)
りそなグループのiDeCoサービスでは「Smart-i」シリーズの投資信託が選択できます。信託報酬は比較的低水準ですが、最安レベルとは言えません。
全世界投資戦略で比較した場合、SBI証券のiDeCoとりそなのiDeCoでは年間約0.09%の信託報酬差があります。
3,000万円の資産で年間コストを比較すると、信託報酬差は約27,000円となり、月割りでは約2,250円の差額が生じます。
この試算では、信託報酬の差額の方が給付手数料よりも大きくなります。そのため、単純に手数料無料を目的としてりそなに移管するメリットは、資産額が大きい場合には限定的と言えるでしょう。
まとめ(18:15)
iDeCoの受け取り方法には3つの選択肢がありますが、年金受け取りは現在1割程度の利用にとどまっています。しかし、今後は年金受け取りが増加すると予想されます。
受け取り方法を選択する際のポイントとして、まず総合的な老後資産設計の中での位置づけを明確にすることが重要です。NISAの活用状況や企業年金の有無も考慮し、公的年金の受給戦略と連動させる必要があります。そして手数料だけでなく、運用コストも含めて総合的に判断することが求められます。
りそなグループの手数料無料化は画期的な取り組みです。この流れが他の金融機関にも波及することで、iDeCo利用者にとってより良い選択肢が増えることが期待されます。
将来的な老後資産設計を考える際は、従来の「税負担軽減のための一括受け取り」という考え方から、「総合的な資産効率を重視した年金受け取り」という考え方への転換も必要になるかもしれません。自身の資産状況や将来設計に応じて、最適な受け取り方法を検討することが重要です。
またこちらの動画「なんでiDeCoやらないの!?NISAだけの人は要注意!老後資金に『決定的な差』が出る理由」では、NISAよりもiDeCoがおすすめな理由を詳しく解説していますのでぜひご覧ください。