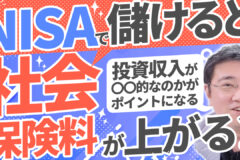NISA貧乏を防ぐ!投資と生活の最適解
本記事では最近話題になっている「NISA貧乏」というキーワードを取り上げなぜ一部の人が投資に偏りすぎて生活が苦しくなってしまうのか、そしてそのような「貧乏思考」からどうすれば抜け出せるのかを解説します。
投資初心者や新NISAを始めたばかりの方、そして将来の不安から貯蓄に走っている方にとってバランスの良いお金の使い方を学ぶ絶好の内容です。
キーポイント
NISA貧乏とは何か?(00:00:00)
「NISA貧乏」という言葉を聞いたとき、あなたはどう感じましたか?一見、矛盾しているように思えます。NISAは資産形成のための制度でありお金を増やす手段であるはずです。それなのになぜ「貧乏」という言葉がくっついてくるのでしょうか。
実はこの「NISA貧乏」という言葉はNISAを使った投資によって生活費が削られ日常の満足度が下がってしまっている状態を指しています。本来NISAは非課税制度を活用して資産を増やすためのものでありそれ自体が悪いわけではありません。むしろ貯蓄や投資を通じて将来の安心を得ることは正しい選択です。
ではなぜ「貧乏」と感じてしまうのでしょうか?それは自分の経済状況や生活スタイルに合わないペースで投資をしているからです。全力でNISAにお金を突っ込んでいる人の中には「今の生活が苦しい」と感じてしまっているケースがあります。
これは「節約貧乏」と似た構図であり、目的が見えないままに節約や投資にのめり込んでしまうとかえって精神的な負担が大きくなります。結果として将来のための投資が現在の生活の満足度や幸福度を著しく下げてしまうのです。
このような状況に陥らないためには自分の投資行動を客観的に見直し「貯めること」や「増やすこと」だけに偏らない生活設計が必要です。つまり投資と日常のバランスが取れているかを常にチェックし「本当に自分にとって必要な支出と投資か?」という視点を持つことが大切といえるでしょう。
「今の生活」も大切にする思考のすすめ(00:05:39)
投資の目的が「将来の安心」であるならばそこに至るまでの「今」を犠牲にするべきではありません。マネーセンスカレッジが繰り返し伝えているのは「バランスの取れた資産形成」です。
生活費を削ってまで投資にお金を回すことが必ずしも最善とは限りません。むしろ「今」を大切にできなければ将来に備える意味すら薄れてしまいます。「今しかできないこと」「今しか味わえない経験」にお金を使うことも人生を豊かにする大切な要素です。
たとえばお子さんの成長や家族との時間、友人との交流、旅行や趣味などに投資することは将来後悔しないための「今の使い方」でもあります。
もちろん将来のための備えが不要だという話ではありません。しかし将来の安心のために「今」を過度に削ってしまうと幸福の総量が減ってしまう可能性があります。
そのため資産形成は「今を大切にしながら将来も安心できる」バランスを追求すべきです。そのためには自分自身のファイナンシャルプランを持ち現在の収入や支出を正しく把握したうえでどれだけ投資に回せるのかを明確にしておく必要があります。
この考え方がなければ「NISA貧乏」のような状態に陥りやすくなってしまうのです。
日本のGDPが上がっている?(00:08:26)
2024年10〜12月期のGDPが年率換算で2.8%増加したというニュースは一見すると日本経済の回復を感じさせるポジティブな話題に映ります。しかし「なんでこんなに皆が生活を苦しんでいるのにGDPは上がっているの?」という疑問が湧きます。
まず押さえておきたいのはGDP(国内総生産)とは「国内で生産された財やサービスの付加価値の合計」を指します。そしてこのGDPには輸入はマイナス項目として計算されます。つまり輸入が減るとGDPは増えるという構造になっているのです。
今回のGDP増加の一因として挙げられていたのは「輸入額の減少」です。これは「個人消費が減ったから輸入が減った」可能性が高くその結果として見かけ上GDPが押し上げられたという構図です。決して「みんなが豊かになって消費を増やしたからGDPが上がった」というわけではありません。
ここで重要なのは日本の個人消費がGDPの約55%を占めているという点です。アメリカでは60〜70%に達しており比較的消費に積極的な国と言えます。一方の日本は長年のデフレや将来不安の影響から節約志向・貯蓄志向が強くそれが個人消費の低迷を引き起こしています。
個人消費が下がるのはなぜか(00:09:21)
個人消費が下がっている要因として次の三つのポイントが挙げられています。
一つ目は手取り収入が増えないという問題です。実際には世帯収入は増えているもののそれは共働き世帯の増加によるものであり「生活の余裕ができたから収入が増えた」というよりは「共働きしないと生活が成り立たないから収入が増えた」という背景があります。これは生活の質の向上とは言いがたく多くの家庭では「余裕のなさ」を感じながら日々を過ごしています。
二つ目は物価の上昇です。食料品やエネルギー価格が高騰しており特に生活に密着した商品ほど値上がりが激しい傾向があります。これは「コストプッシュ型インフレ」と呼ばれる現象で企業が原材料やエネルギーコストの上昇分を価格に転嫁しているために発生します。そのため消費者は「今はなるべく支出を控えよう」という心理に陥り個人消費がさらに縮小するという悪循環に陥っているのです。
三つ目は将来への不安=長生きリスクです。老後の生活に対する不安から貯蓄に回す傾向が強まり「今は我慢して将来のためにお金を蓄えておこう」という心理が働くのです。このような思考が強くなるとますます消費は抑制され経済全体にとってはマイナス要因になります。
これらの問題は本来なら政治が対応すべきと指摘できます。たとえば税収が過去最大なのに減税が行われない点、食料品や公共サービスの価格が高騰しているにもかかわらず有効な対策が講じられていない点など政策の遅れが庶民の生活を苦しくしている現実に対してマスコミは「NISA貧乏」といったキャッチーな言葉で煽るのではなくもっと構造的な問題に切り込むべきではないでしょうか。
健全な資産形成のためのバランスの取り方(00:18:39)
「NISA貧乏」にならないために最も重要なのは「生活防衛資金」と「ファイナンシャルプラン」をベースにしたバランス感覚です。
まず生活防衛資金とは何かあった時のためにすぐに使える現金を指します。一人暮らしの人なら最低でも50万円、家族がいるなら100万〜200万円、個人事業主ならその1.5〜2倍ほどを目安に生活防衛資金を用意すべきです。これがあることで精神的にも余裕を持って投資に取り組むことができるのです。
また「積立金額を自動化する」ことも重要でしょう。自分の意志で毎月振り込むのではなく口座から自動で引き落とされるように設定することで継続が習慣化され感情に左右されずに淡々と積立が続けられるようになります。たとえば40歳の人が65歳をゴールにして25年間の長期積立を計画しているならたった半年や1年の値動きに左右される必要はありません。
さらに「投資に偏りすぎている人」は注意が必要です。たとえば、全資産の90%を投資に回しているような状態はさすがに行きすぎです。これは投資がゼロだった人がいきなり極端に振れることで起きる現象ですが非常にリスクが高く生活の安定性を欠いてしまいます。
そのため投資比率の目安としては100万円の資産があるなら50万円を投資に回すというようなバランスが理想的とされています。また資産が増えてきた場合でも1000万円のうち900万円を投資に回して100万円を現金で残すといった設計であれば問題はありません。
重要なのは「自分のライフスタイルや将来の支出に応じた現金の備えを持った上で投資を行う」ことです。それがあってこそ健全で長続きする資産形成が可能になるのです。
まとめ
投資と貯蓄は「手段」であって「目的」ではありません。今の生活の満足度を高め将来に向けた安心感を得るための手段であるはずです。そのためには自分の生活と資産のバランスを見直し感情に流されず理性的な判断を下せる仕組みを作ることが大切です。
生活防衛資金を持ちファイナンシャルプランを立て必要に応じて投資額を調整し自動化する。こうした取り組みを一歩ずつ進めていけば「NISA貧乏」とは無縁の豊かで持続可能な人生を歩むことができるでしょう。
またこちらの動画「《焦らなくて大丈夫!》新NISA 1,800万円を使い切るより大切なこと」では新NISAで枠を使い切る必要がない理由を解説していますのでぜひご覧ください。