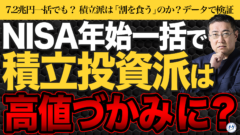子どもNISAで子どもに資産を残していくために必要な考え方3選
最近発表された金融庁の税制改正要望の中に、子どもNISA的なものが含まれていました。実際に子どもにお金が移っていくとなれば、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんからお金が流れていくことになります。
マネーセンスカレッジでは、資産形成というのは本来、家族間や世代間で考えた方がいいという考え方を提唱しています。ただし、そこに行き着くためには、まず自分自身が経済的に自立しなければなりません。学費を払ったり子どもを育て、自分自身の老後資金をしっかり確保できなければ、その先に資産を渡すことはできないからです。
ファイナンシャルプランから見た相続の考え方(1:37)
多くの方は、お子さんやお孫さんに資産を渡すことについて、相続税対策だと考えているかもしれません。しかし実際はそうではありません。
ファイナンシャルプランニングを作成していくと、死ぬ間際にお金をあまり残したくないという考え方があります。今を楽しんで老後も不安がない方がいい、全部使い切ればいいのではないかという考え方には納得できる部分があります。しかし、その考え方を持ってしても、やはりある程度は残さなければなりません。いつ死ぬかわからないからです。これを長寿リスクと呼んでいます。
平均寿命が80代後半になる中、90歳で亡くなったとすると、30歳の時に生まれた子どもでも60歳になっています。その時にまとまったお金をもらっても、老後の足しにはなるかもしれませんが、おじいちゃんからおじいちゃんにお金が渡っただけで、社会的な意義や生産性はそれほど高くありません。もっと若い世代に資産が移った方が、世界への貢献度が大きくなる可能性があります。
本人から考えても、若いうちにお金をもらった方がいいはずです。お金がないから一生懸命働いていたのに、いつの間にか亡くなった時にドンともらっても、「こんな苦労しなくて済んだのに」と思うでしょう。それよりも、わずかなお金でも早めに渡して長期運用しておいた方が、その子も資産の成長を見ることができますし、管理をすることで力もつきます。
早くに資産運用に触れておくと、ファイナンシャルプランの大切さが分かってきます。子どもや孫に渡すと自分自身のお金がなくなってしまうと心配されるかもしれませんが、それは家族間の中だけで考えているから問題なのです。資産というものは世代間にわたって一つのものとして存在していると考えることができます。
自分自身の資産から、子どもや家族という単位で世代間で考えることをすれば、運用方法もまた変わってくるのではないでしょうか。
金融庁の要望(5:23)
現状、NISAの対象商品の拡大と制度の拡充について、金融庁から要望が出ています。その中には子どもの支援として、つみたて投資枠の対象年齢を見直して拡充してはどうかという提案があります。
現状のNISA制度は18歳以上が口座開設できる仕組みになっていますが、これを拡充して、例えば0歳からにすれば昔のジュニアNISAのようになります。
過去のジュニアNISAは成人のNISAと分断されてしまっていたため、そのまま投資を継続することができませんでした。しかし、本来推進したいのは長期投資です。そのため、ジュニアNISAを新たに新設するのではなく、今あるNISAの中で子どもからすでに使えるようにしておこうという案が出ています。
ジュニアNISAが使われなかった理由は単純に使いづらかったからです。その意味では、今回の改正はおそらく進んでいくのではないかと思われます。
子どもNISAになってくると、大人が子どものために拠出するということが基本的になっていると考えられます。ただし、親が投資していないという形になってくると、子どものNISAは使われないでしょう。やはりここは親御さんからの引き継ぎが重要です。では、その知の継承はどんなものを継承した方がいいのかということも考えていく必要があります。
子どもに資産を残すために必要な考え方3選(8:12)
ここで3つ気をつけることがあります。
まず一つ目は、「誰もが運用できる方法を選択する」ということです。子どもが成人になった時も続けられる方法の方がいいでしょう。親ができていなければいけないというか、少なくとも行動はしていなければなりません。お子さんやお孫さんができる運用方法でなかったら、それは引き継げません。
このチャンネルを見ている方も、将来必ず来る老後生活に向けて資産運用や資産形成をしているはずです。お子さんだって変わりません。今後、年金財政がすごく急激に上がるという未来予想はないため、現代において行っている老後資産設計というものは、子どもや孫の時代でも必要でしょう。
では、その方法は何だろうとなってくると、今の時代においてはアセットアロケーション運用しかありえないと考えています。トレーディングは進化が早く、AIやアルゴリズムトレードなど最先端になっていきます。その中でも、アセットアロケーション運用という考え方は一定程度残ると思います。
アセットアロケーション運用を採用している全世界投資のコンセプトとしては、全世界の経済成長に乗っかろうということです。この全世界の経済成長というのは、歴史から見て止まったことはありません。200年という期間で見たとしても、崩れたのは第一次世界大戦と第二次世界大戦の2回だけでした。その期間以外はずっと経済成長し続けていたため、今後もそうなるだろうと予測しています。これだったら、お子さんの時代もお孫さんの時代も、大丈夫ではないですかと自信を持って伝えることができます。
二つ目は、「いつの時代でも通用する投資戦略を選ぶ」ということです。この「時代」には二つの意味合いがあります。一つは世界の情勢が変わったとしてもということ、もう一つは自分の年齢によって変わる投資戦略ではないということです。
全世界投資の方法論というのは、老いも若きも誰でも同じという投資方法です。そもそも若いうちは株式だけでいい、老後に入るにつれて債券にシフトしなければならないというのは、本当に合っているのでしょうか。
年齢やお金の額などは、世界の経済から見て関係ない属性です。株式市場や債券市場で取引している人たちは、あなたの属性に関係なく、誰からの注文かも分からないという状態で取引しています。ということであれば、基本的に属性は関係ないはずです。世界の経済成長に合わせればいいだけの話であって、自分自身の年齢に合わせる必要がないのです。
とはいえ、高齢に行くに従って、年金が足りないので取り崩さなければならないとか、お子さんの学費を払わなければならないとか、必要なお金が目の前に迫ってくるからです。では、その分だけ現金化しておけばいいのです。使うから現金化する。使わないのだったら別に現金化する必要はありません。
よく例に挙げるのは、バフェットさんが90歳超の奥様に対して、10%は国債で、90%はS&P500のインデックスに投資をしなさいと遺言書を書いた話です。本来、安全性を高めなければいけないはずですが、使える金額は大量にあるから、10%だけでも使い切れないのです。
つまり、投資の方法論というのは一つでいいし、どの時代でも通用するものでいいということです。債券シフトや現金シフトなどを考えるのは、使うお金が分かっている段階であらかじめ早めに現金化しておくということです。目安としては3年以内という話をしています。
三番目は、「お子さんの金融リテラシー教育」です。マネーセンスカレッジでは、お金の勉強の順序として、使う、稼ぐ、貯める、増やす、守る、分かち合うという6段階があるという話をしています。未成年まではもう最低限、使うだけで問題はありません。
少なくとも中学生まで、義務教育までの間は「使う」教育を徹底的にしたらいいと思います。無駄なものを買わないとか、トレードオフといってこちらを買うとこちらが買えないとか、物を大事に使うとか、そこからです。
まず使うというところがちゃんと適切に使えるようになれるということが大事だと思います。それが実践的に学べるのが、この使うというところなので、それはもう徹底的に親御さんが付き添って、使うという教育をされたらよろしいのではないかなと思います。
「増やす」というものは、先ほど言った誰でもできる運用方法といつの時代も通用する運用方法であれば、増やすことを教えるのは簡単です。やることは簡単で、やることさえできれば結果はついてきます。少なくとも投資の方法論というのは難しくないので、大人になってからで十分です。
まとめ(20:57)
これまで3つのことについて話をしました。誰でも運用できる投資方法を選ぶこと。二つ目に、いつの時代でも通用する投資戦略を選ぶこと。そして、子どもへの金融リテラシー教育というのは使うだけでいいですよということです。
またこちらの動画「子供の金銭教育で気をつける点はありますか?」では、お子さんの金融リテラシーを高めるのに役立つ情報をお伝えしていますのでぜひご覧ください。