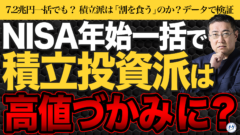NISAつみたて投資枠の選択肢拡大!広がる投資対象のメリットとリスク
NISAのつみたて投資枠の対象が広がる可能性について、金融庁から興味深いニュースが出てきました。
これは投資家にとって非常に重要な変化となる可能性があるため、詳しく解説していきます。
スタート(0:00)
金融庁では7月まで3回程度開催されている「NISAに関する有識者会議」というものがあり、この会議でNISAの現状や改善の余地について議論が行われています。その中で、金融庁からインデックスの対象をもう少し広げてもよいのではないかという提案がありました。
委員からの主な反対意見はなく、積極的に増やすべきであるという委員もいたことから、金融庁としては拡充に向けて実際に作業を始めていくという方向性が示されています。
つみたて投資枠 選択肢拡大について(1:46)
NISAは枠が大幅に広がり、恒久化もされたことで使い勝手が良くなってきました。しかし、つみたて投資枠で投資できるものについてはかなり制限が入っているのが現状です。
現在はつみたて投資枠では株式型の商品しか認められておらず、バランス型の場合は債券やREITなども購入できますが、単体で購入できるのは株式だけとなっています。この制限を緩和してもよいのではないかという議論が出ているのです。
全世界投資という投資手法では、日本債券、海外債券、日本株式、海外株式、そしてREITや金なども含めて幅広く投資することで、世界の経済成長に乗っかっていくという考え方があります。この方法により、投資する対象が世界全体となるため、一つの会社や一つの国、一つの地域で何か起こっても、全世界への分散投資によってリスクを軽減できるという利点があります。
過去200年程度のデータを見ても、世界経済は指数関数的に成長を続けており、株式の恩恵を受けながら投資ができるという実績があります。
現在、つみたて投資枠で投資できないものがあります。それは日本の債券、先進国の債券、日本のREIT、海外のREIT、金などです。これらには投資できず、株式のみが単体で購入可能となっており、対象となる指数も限られています。
どこまで拡充するのか?(3:17)
有識者会議では、日本債券については変更してもよいのではないかという積極的な意見もありました。金融庁が提出した説明資料には「若年層から高齢層まで、あらゆる世代がそのリスク特性に応じて安定した資産形成ができるようにすることが必要である」として、リスクが低くより安定的な運用が望める商品も含めて、対象商品の拡大をする余地がないか検討されるべきであるという文言も記載されています。
委員の中では、日本国債は安定運用の必須なものであり、日本国民に広く購入できるようにするのが望ましいという意見もありました。国債ファンドだけでなく、個人向け国債も当然入ってもよいでしょうし、これから金利が上がっていく段階で、債券投資の妙味が薄まっている中、個人向け国債の変動10年なども選択できるようになることが期待されます。
2024年12月には財務省から変動利付債というものを作ろうという発表もありました。これは短期債券になる予定で、大体2年から5年程度の期間になると思われますが、このような商品を購入できるように一部解放することも必要でしょう。
さらに、ESGに特化したインデックスについても議論されています。環境、社会、ガバナンスに配慮した投資への関心が高まる中、ローカーボンなどの環境に配慮した投資を行うインデックスが選べるようになることも検討されています。
実際、ESG関係のインデックスは多数存在しており、MSCIやS&P、モーニングスター、フィッチなどの大手指数会社がESGに関してかなり詳細な分析を行っています。例えば、MSCI日本株式のESG指数「MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数」などは、比較的良好な成績を残しています。
こうした投資にウェイトをかけたいというニーズは今後増えていくと予想され、インデックス投資の中でも世界的に増加傾向にあることから、選択肢の拡大は良い方向性だと考えられます。
一方で、なぜ日本国債が今まで入ってこなかったのかについては、NISAが拡充された際に債券にシフトしてしまうのではないかという懸念や、金融リテラシーの重要性という観点から様々な議論があったと思われます。しかし、NISA内で購入できないとなると、国債を購入してリスクを抑えたいというニーズには答えられないという問題もあります。
投資商品を選定する前にすること(10:02)
選択肢が増えることは良いことですが、同時に選択が難しくなるという側面もあります。指数が増えることで、自分で選べる方には歓迎される一方で、日本国債が入ったからといって安易に「面倒だから国債だけでいい」と考えるのは適切ではありません。
投資商品を選定する前に、まず何のために投資するのかという目的を明確にする必要があります。これがファイナンシャルプランということになります。
NISAを使う理由についてのアンケートでは、7割以上の人が老後資金と答えています。であれば、その老後資金がどれだけ足りないのか、どれだけ必要なのか、いつまでにいくら必要なのかをしっかりと設定しなければなりません。
そのために使う金融商品を決める際に、貯蓄だけで十分なのか、国債だけで足りるのか、それでは不十分であるならば一定のリスクを取りながらも投資に向かう必要があるのかを検討する必要があります。
一定のリスクを取る場合でも、安全に長期投資・資産分散・時間分散を取り入れることが重要で、そのための投資戦略が必要になります。特に長期投資については、戦略が欠かせません。
株式だけが良いという考え方もありますが、値動きが激しいため、その変動をカバーするような投資方法も検討すべきです。年金資金などが運用されているGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が採用しているようなアセットアロケーション運用が、個人投資家にとっても適している可能性があります。
アセットアロケーション運用を行うために必要な金融商品を考え、そこに一定のアレンジを加える(ESG投資など)ということは有効な手段です。
老後資金を貯めたいのであれば、いつまでにいくら増やす必要があるのか、使っていく間も投資を継続していかなければならない場合にどうするのか、安定的に運用したい場合はどうすれば良いのかなど、金融知識を深めていくことが重要です。
金融商品の選定は一見すると最初に考えるべきことのように思えますが、その前にやらなければならないことが多くあります。選択肢が広がって選ぶのが難しくなったとしても、投資戦略をしっかりと持っていれば選びやすくなり、迷わずに済むでしょう。
ファイナンシャルプランがあっていくら老後資金が必要で、そのためにアセットアロケーション運用を取り入れた場合に、どのような金融商品が適しているかは自然と答えが出てきます。選択肢が広がったとしても迷わないのです。
この指針がないと、選択肢が広がるにつれて考えることを避け、「国債でいいや」となってしまいがちなので、注意が必要です。
有識者会議でも言及されていますが、デフォルトで何を設定するかということの影響は大きいものがあります。例えば、企業型確定拠出年金ではデフォルトのファンドを選択でき、それを元本保証型にしておくと影響が少ないが、株式型にしておくとそちらに多くの人が流れてしまうということがあります。
自分自身で設定していないまま投資されるのは問題ですが、行動経済学の観点では、デフォルトの影響力は強いものがあります。選択ができることは一見良さそうですが、指針を持っていない方にとっては難しい面もあります。
そういう意味では、ある程度の父権主義も必要なのかもしれません。
まとめ(14:13)
NISAに関する有識者会議において、金融庁が提出した資料や有識者の意見を踏まえ、つみたて投資枠で使われるインデックスについて拡充される動きが出てきています。特に反対意見もなかったことから、おそらく作業チームが作られて報告書が上げられ、実際にこのような変更が行われるという発表が今年中には出てくると予想されます。
これは非常に良い流れだと言えるでしょう。全世界投資・アセットアロケーション運用を行う上で、アセットアロケーション運用には必須のアセットがあるため、そうした商品も増やしていただきたいところです。
またこちらの動画「【資産を増やす】初心者が絶対に守るべき!NISA活用10ヶ条」では、NISAを利用しているならぜひ守ってほしい10ヶ条を詳しく解説していますので、併せてご覧ください。