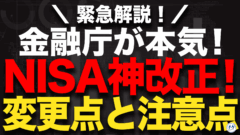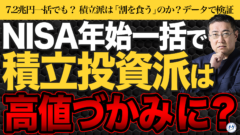不動産クラウドファンディング破綻から学ぶ、真の不動産投資とは
不動産クラウドファンディングの破綻ニュースが話題となっています。不動産投資といえばREITが代表的ですが、今回の破綻事例を通して、クラウドファンディングとREITの違いや、真の不動産投資について考えてみましょう。
過去にもクラウドファンディングについて解説してきましたが、今回は破綻という事態に加えて、配当金の未払いなどのニュースも出てきているため、投資家の皆さんに注意喚起も含めて解説します。
ダイムラーファンド破綻の事例(0:58)
今回ニュースに上がったのは「ダイムラーファンド」という会社で、代表者が亡くなったと報道されています。取締役が不在の中、破産申請が行われました。
7月20日にニュースが出ましたが、破産申請は7月15日に行われており、手続きはまだ続いている状況です。特に土地取得を行っていたため、土地売却には多くの時間がかかると予想されます。
債務超過の状態で破産宣告されているため、土地が売却できたとしても、投資家の出資金が戻ってくる可能性は極めて低いでしょう。
この不動産クラウドファンディングは「開発型」のタイプでした。沖縄のジャングリラ周辺の民泊需要を見込んで周辺エリアの土地を取得し、民泊リゾートを開発する計画でした。運用中のファンドについてはまだ配当が支払われていない状況でした。
不動産クラウドファンディングの運営会社が破綻したのは、おそらく今回が初めてのケースです。
不動産クラウドファンディングとは(2:48)
不動産クラウドファンディングは、個別の不動産に出資して配当を受け取る仕組みです。運営会社の設定が基本的に優先されるため、スキームや透明性については運営会社による部分が大きく、どこを選ぶかが重要になります。
運営会社自体がどのような財務状態なのかは最低限調べる必要があります。債務超過の状態では、そもそも投資対象になりません。債務超過の上場株式会社はほとんど存在しませんが、もしそのような会社があったとしても、いくら配当が高くても株式投資はしないはずです。
12%といった高い利回りを謳っていても、それに飛びつくのは投資家としての責任を問われても仕方がないでしょう。新しい金融商品や投資手法については、しっかりと調べることが必要です。
ニュースに出ていた投資家の声として「定期預金の感覚だった」というものがありましたが、8%から12%といった利回りで定期預金の感覚というのは明らかに認識が甘すぎます。そのような高い利回りの定期預金があれば、誰もが全力で投資するでしょう。
実際に、不動産クラウドファンディングをちゃんと運営している会社もあります。既存のビルが建っていて、それを取得し、その収益の一部を分配するという基本的なスタイルが一般的です。
ただし、運営会社の規模はREITなどと比べて非常に小さく、地震リスクなどの災害によってピンポイントで被害を受けた場合、すぐに破綻してしまう可能性もあります。
2017年の法改正で資本金要件が一部緩和されたため、多くの会社が参入してきました。インターネットとの競合も生まれ、小規模不動産特定共同事業として登録する会社が増加しました。今回のダイムラーコーポレーションも、この2017年の緩和によってできた会社です。
投資家保護の観点から、こうした事業を営むためには資本要件や透明性の確保など、一定の規制が必要かもしれません。いずれにしても、このような投資商品を扱う場合は十分に調べることが重要で、運営会社が債務超過になっているかどうかぐらいは調べられるはずです。それができない人は、こうした商品には手を出さない方が良いでしょう。
REITとは?(6:15)
REITは日本と海外のものがあり、REITに投資しているファンドに投資することで、全世界投資という投資戦略の一部として購入できます。
REITも結局は不動産に投資していて、その不動産から家賃収入などを得て、それを配当に回していく仕組みです。法律によって90%以上の配当を出さなければならないと定められており、投資法人という法律によって定められた方法で作られているため、比較的安心して投資できます。
上場もされているため透明性が確保されており、税制上の優遇効果もあります。また、上場しているため投資家からお金を集められる仕組みになっています。
不動産事業をされている方からは「REITは利回りが低いからありえない」という声もあります。REITはその時々によってレバレッジが異なりますが、大体2倍程度で運用されています。現在のREITの利回りは大体3〜5%程度で、8%を超えるものは少ないのが現状です。
しかしREITこそが真の不動産投資と考えられます。不動産クラウドファンディングや個別の不動産投資は、実際には「不動産事業」なのです。
投資とは、お金を投資したらほったらかしにしていても基本的に運用され続けるものです。しかし、クラウドファンディングは事業者を選定しなければならず、大体1年間程度の期間で資金が戻ってきて、配当もちゃんと確認する必要があります。事業規模も考慮しなければなりません。
個別の不動産投資についても、不動産を購入したり、入居者を見つけたり、銀行から融資を受けたりと、様々な作業が必要になります。ほったらかしにはできません。入居者が退去した場合には何かしらの対応が必要で、付加価値をつけて良い状態にしてから新しい入居者を迎える必要があります。これは明らかに事業であり、経営と変わりません。
クラウドファンディングはそうした作業を運営会社に丸投げできる点がありますが、それでも個別の不動産案件に対するクラウドファンディングのため、リスク的には高い状態になります。
開発型については特に注意が必要です。事業に投資しているため、本当にゼロになってしまう可能性もあります。一方、既存のビルがあってそこから収入を得るものであれば、それはREITと変わりません。それならば分散投資をした方が良いでしょう。
J-REITファンドであればJ-REIT指数に投資しているため、分散効果もあります。しかも保有しているものは一級品です。もちろん大きな物件を購入するには多額の資金が必要ですが、小さな金額で大きなものにも投資できるという点はありますが、それができないのであれば自分で投資すれば良いという考えもあります。
まとめ(13:00)
不動産クラウドファンディングは基本的に投資とは呼べず、事業であることがほとんどです。本当に純粋に不動産投資と呼べるものは、REITもしくはそのREITに投資しているREITファンドのどちらかぐらいでしょう。
自分自身で見極めができるのであれば、不動産クラウドファンディングもサテライト運用として一応可能だとは思いますが、ほとんどの方は見抜けていないのではないでしょうか。見ようともしていないのが現状です。
投資対象を見ようとしないことが最大の問題点です。投資はほったらかしにできるものですが、事業だったらなおさら注意深く見る必要があります。そこをちゃんと見てあげるという投資家の姿勢が大事です。
本当に不動産事業をしたいのであれば、不動産事業の株式を購入することをお勧めします。流動性、税制、信頼性、透明性という意味においてはREITに軍配が上がります。
自分のポートフォリオに不動産投資を加えたいのであれば、REITから考えていただければと思います。REITは上場投資信託としてありますが、手数料がかかってしまうため、REITに投資しているREITファンドに投資される方が良いでしょう。REITファンドであれば月100円から投資でき、積立投資の対象とすることもできるため、敷居も低くなります。
またこちらの動画「みんなで大家さん業務停止!不動産クラファンで失敗する人の特徴とリスク」では、不動産クラウドファンディングのリスクや重要なポイントを解説していますのでぜひご覧ください。