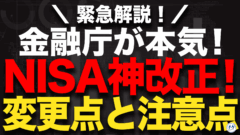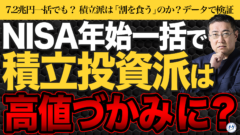インフレ時代を生き抜く!お金持ちが実践する最新”%思考”の極意
マネーセンスカレッジでは「金額で考えるな、パーセントで考えろ」と伝えています。このパーセントで考えるという思考法には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
投資や経済のことを考えていくとパーセントで考える方がうまくいきやすくなります。これは消費者脳から投資家脳になるためのコツでもあります。投資を始めて間もない方や、経済のことを学ぼうとしている方は、この考え方を取り入れるだけで見方が変わります。
消費者脳と投資家脳(1:14)
家計管理や投資の評価において、金額でやる場合とパーセンテージでやる場合では、大きな錯覚が起きることがあります。
多くの人の思考方法は金額、つまり額面で考えます。1万円上がった、家賃は10万円、毎月2万円の貯金といった具合です。
一方、投資家脳の思考方法では、割合やパーセントで考えます。収入が3.3%上がったと考えることで、インフレと比較することができます。家賃は収入の20%と考えれば、収入の規模によって金額は変わるものの、20%であれば生活は破綻しません。収入の10%を貯蓄すると考えることで、ライフサイクル仮説という考え方にも進めることができます。
パーセントで考える重要性としては、的確な判断ができること、バランス感覚が養われること、自分自身の経済状況を正確に把握できることが挙げられます。長期的な資産形成の基礎となり、将来に向けた考え方も取り入れやすくなります。
「パーセンテージで考える」6つのメリット(3:21)
パーセントで考える6つのメリットをまとめました。
まず1つ目は、感情に流されず冷静に判断できるという点です。昇給時に給料が1万円上がったと考える人は、お小遣いも1万円上がると考えがちです。しかし給料が3.3%上がったと考えれば、お小遣いも3.3%上がるという風に考えることができます。その割合に応じて考えることで、冷静かつ客観的に判断できます。収入が変わったとしてもパーセンテージで考えることによって、一定の比率で支出を管理することもできるので、家計管理には重要な考え方になります。
2つ目は、他人と比べるストレスから解放されるという点です。金額で考えると、同僚の家賃が6万円で自分の家賃が10万円だと、損しているような感じがするかもしれません。しかし、同僚の家賃比率が30%で自分自身の家賃比率が20%であれば、自分自身の家賃の金額は確かに高いかもしれませんが、総収入から考えるとそれほど高くありません。バランス感覚を取り戻すことができます。
3つ目は、アクシデントに強い家計設計ができるという点です。経済の中では基本的にパーセンテージで考えられることが多くなっています。公的支援の目安を見ると、傷病手当金や労災の支給率は給与金額に対して3分の2、つまり66%です。これに合わせて自分自身の生活を設計しておけば、基本的には問題ありません。世の中の仕組みや経済がパーセンテージで動いているので、自分自身の家計もパーセンテージで考えると、それに合わせてリンクすることができます。
生活防衛資金の考え方として3ヶ月分から6ヶ月分ぐらいの生活費を用意しておくことで対処できます。数千万級のアクシデントに関しては保険で対処する必要があります。日々の生活においては、生活防衛資金の年収に対する割合や月収に対する倍率で考えることで、基本的には問題ありません。
4つ目は、支出の予算感が把握しやすくなるという点です。金額ベースで考えると、家賃が8万円、食費が5万円、光熱費が2万円という風に考えがちですが、パーセントベースで考えると、家賃は収入の25%以内、食費は収入の15%以内という風に考えることで、予算感がバランスよく取れる形になります。収入が変動した場合でも、そのパーセンテージで考えることによって、金額が把握しやすくなります。
月収30万の方が家賃収入25%であれば7万5000円になりますが、月収40万であれば25%は10万円に相当するので、2万5000円アップすることができます。その分だけ家族の夢や希望を叶えることができますし、便利なものや通勤時間を短くするといったことができるようになります。
5つ目は、ライフスタイルにあった資産形成ができるという点です。固定額管理の場合は、毎月3万円や1万円を投資に回すといった始め方が多くなっています。しかしパーセントで考えると、収入の何パーセントを投資するということができるようになります。収入の10%を投資に回すことで、将来の老後資産設計において、20代の方が始めることによって十分資産形成できてしまいます。
自分自身の手取り収入から何パーセントを貯蓄していく、投資をしていくという風に考えると資産形成の規模が測りやすくなります。月収が変わったり、年収が変わったり、夫婦2人の共働きになった、またお子さんを授かって休業しているというようなことにおいても、パーセントの管理をすることによって、フレキシブルに変更することができます。パーセンテージで考えると、自分自身の生活レベルに合わせた投資や貯蓄ができるようになります。
6つ目は、相場の変動に強くなる心の体制が育つという点です。金額で考えると、10万円投資をしていたら1万円下がった、1000万になっていると100万下がったという形になります。しかしこれは10%という割合は変わりません。経済はパーセンテージで動いているので、資産規模に関わらずパーセンテージで考えた方が、額面が大きくなったとしても適切に判断することができるようになります。資産規模はある程度大きくなっていきますが、金額で考えてしまうと動揺してしまいます。パーセンテージで常日頃から考えておくと、その変動はそれほど大きく感じることはなく、心の体制を育てることができます。
「パーセンテージで考える」4つのデメリット(13:02)
まず1つは、絶対金額が分かりにくいということです。パーセンテージで考えると、最終的な金額は想像できません。金額自体をパーセンテージから金額に落とし込むということも必要になってきます。家賃は収入の25%という風に考えた時、25%だけでは金額は分からないので具体的な行動に移せません。自分自身の収入に対して25%をかけるという一手間がかかってしまいます。
7%の期待利回りは結構小さい数字に聞こえますが、3000万で7%という風になってくると、年間210万円もリターンがあります。金額に置き換えることによってインパクトを感じることもできるようになるので、パーセンテージだけで考えるわけではないということに注意が必要です。
また相対的な評価になってしまうということもあります。期待利回り7%という話をしていますが、この7%は小さいという風に言いましたが、逆に大きいと感じる方もいます。元本が小さいと当然リターンは少なくなります。100万円であれば7万円、10万円であれば7000円、1万円では700円です。元本についてもある程度見てあげなければいけません。パーセンテージだけで見るわけではないということです。
さらに複利効果を過小評価してしまうという方が結構多くいます。7%の利回りという風に言うと、100万投資して7万円か、1000万でも70万しかないのかと考えがちです。しかし7%の複利利回りで計算すると10年以下でできてしまいます。その意味では72の法則を覚えておくとよいでしょう。2倍になるための期間は72÷利回りのパーセンテージで求められます。期待利回り7%であれば約10年で2倍になるということです。この違いについて理解するということもなかなかしづらいので、過小評価してしまうという危険性もあります。
4つ目は、金額が大きくないとパーセンテージで考えるとモチベーションが上がらないという方もいます。毎月の積み立て金額が1万円から1万1000円に上げられる場合、その1000円の上昇は7%で700円かと感じたりすることがあります。少額であってもパーセンテージでは動いているのは事実であり、その桁を1個上げることができればものすごい大きな金額になります。経済活動は小さなところの積み重ねでもあります。小さい金額から積み上げていくことによって資産形成や資産設計が生まれていきます。
まとめ(17:54)
経済の世界はパーセンテージで動いています。売上目標であれば前年比何%アップといった形で考えられます。経済がそういう風に動いているため、お金の管理に関してもパーセンテージで考えると、そことリンクしやすくなります。
常日頃はお金を金額で考えることが多いですが、計画を立てる時や俯瞰してみる時にはパーセンテージで考えるという癖をつけることが重要です。そうすることで自分自身のバランスが保ちやすく、将来のことを考えやすくなります。消費者脳から投資家脳へ、またお金のリテラシーを高めるといった方向に向かうことができます。
またこちらの動画「72の法則だけじゃない!使えると便利なお金の法則4選」では、投資でよく知られる「72の法則」など一括投資や積立投資に役立つ実践的な法則を解説していますのでぜひご覧ください。